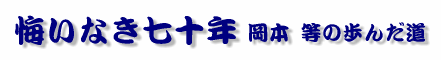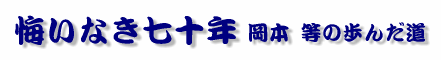| 父島から清水港に上陸した岡本は、汽車で故郷福井へ戻った。
すし詰列車の窓から垣間見る沿線都市 |
| の多くは米軍の爆撃によって破壊され、復興は遅々として進んでいないようす。列車内では第三国人がわ |
| がもの顔でふるまい、日本人は小さくなっていた。長年の抑圧から解放されたのだから無理もない。 |
| しかも、その日本人たちは「お前らが頑張らないから負けたんだ」
と言いたげな冷たい目付きで軍服姿の |
| 岡本等を見つめる。敗戦国のみじめさというものを、父島はもちろん、上陸早々に別の形で味わされ、岡本 |
| は悔しい思いにかられた。しかし、岡本にとっては、それよりも母の安否が心配だった。
とにかく硫黄島以 |
| 後互に音信不通なのだから無理もない。「元気でいてほしい」。車中、岡本はこのことだけを祈り続けた。 |
| 昭和20年7月19日、福井市は米軍のB29爆撃機133機によって焼野原にされた。岡本の留守宅もこれに |
| よって焼失したが、母と姉は無事であった。しかし、岡本はこのことを知る術はなかったのである。 |
| 「ただいま帰りました」 息子の元気な姿に母と姉は「よかったのう」
とかけより、彼の手をしっかりとにぎり |
| しめた。父島から一足先に復員した知人の井上邦夫
(後に福井銀行の重役)から岡本が元気でおり、少し |
| 遅れて復員することは聞かされてはいたが、それでも嬉しかったのである。 |
| その夜、どこで手に入れたのか、母は銀シャリ(白米)を炊いてくれた。副食はよく覚えていないが、味噌 |
| 汁と、久しぶりに味わう白米のうまかったことは今でも忘れられないという、「なんでもいいから腹一杯食べ |
| たい」 と国民の誰もが願っている時代で、都会では「米よこせ」運動が発生、栄養失調で倒れる者が相次 |
| いでいた。 本当に苦しい時代であった。そんななかで、母や姉が元気でいてくれ、自分自身も強運に恵ま |
| れて故郷に帰れたことに、岡本は心から「ありがたいことだ」と感ぜずにはいられなかった。鯖江36連隊へ |
| 同じ日に入隊した日之出小学校時代の同窓は岡本を除いて全員戦死したし、
奉天予備士宮学校時代の |
| 同期も多くが戦死した。岡本はアメリカ軍の猛攻撃が始まる寸前に父島へ飛び玉砕をまぬがれた。また、 |
| 硫黄島へ扶任する際も、輸送船で行く予定(最初は輸送船だったが途中で米軍の攻撃を受け途中で引返 |
| す)を飛行機に変更したため難をまぬがれた。
岡本が乗船する予定だった輸送船は魚雷に撃沈され、
乗 |
| 船していた将兵のほとんどが戦死したのである。「神仏の御加護としかいいようがない」。岡本は生きて帰 |
| れたことについて、いまでもそう言っている。 |