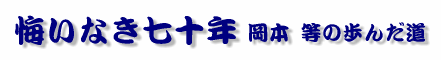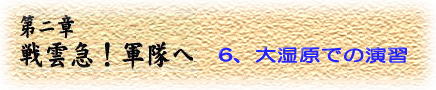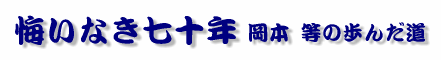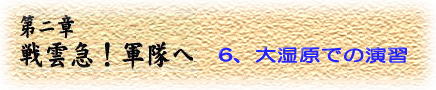| 岡本らが原隊に復帰したのは昭和16年5月。帰隊と同時に |
| 関東軍の特別大演習が実施された。 |
| この年は、支那事変が拡大していくばかりでなく、日独伊が |
| 3国同盟を結び、英米やソ連との緊張がいやが上にも高まっ |
| ていたときである。欧米ではすでにドイツ軍がポーランド、フラ |
| ンスなどを占領、イギリスのロンドンを爆撃。イタリア軍はリビ |
| アからエジプトヘ侵入、日本軍は大東亜共栄圏確立の名目 |
| で仏印へ侵入していた。その当時は侵入とは言わず進駐と |
| いった。領土をおかしたのでありませんよというわけだ。 |
|

満州の広野で演習(奉天予備仕官学校時代) |
|
| そんなときの大演習だから、ソ連はもちろん、米英が大いに神経をとがらせたのはいうまでもない。とくに |
| ソ連はこちらの動きを探るのにやっきとなった。 |
| 岡本の属する第一大隊は一面披を出発、東安省東安に着く。ここから宝清というところを経て、ソ連国境の |
| 饒河へ出る30日間の長行軍をするのである。距離は約400㌔。満州は広い。太陽が東の地平線から上がり、 |
| 西の地平線に沈むところだからスケールが大きい。大湿原を行軍するのだから1日に歩ける距離は決まって |
| いる。3里が目標であった。大湿原とはいえ、平地は歩くのにさほど支障はなかったが、背丈を超す雑草の |
| 生い茂っているところがあって、それを切り払って進むときはたいへんだったし、夜は9月とはいえ厳しい寒さ |
| であった。この大湿原には小高い丘陵地帯がある。そこは底無し沼のようなところがいたるところにあって、 |
| 一歩そこへ足を突っ込むと抜くのにたいへんである。人間の場合はすぐ救出されるが、馬はそんなわけには |
| いかない。重たいからだ。足をめり込ました馬は脱出しようともがく。兵隊も首や胴にロープを巻き脱出を手助 |
| けするのだが、馬はもがくほどに沈んでいく。最後には首だけが残る状態になってしまう。こうなるともう手の |
| 施しようがない。獣医がやってきて拳銃で頭を打ち冥土へ送ってやる。兵隊の中には苦労を共にしてきた愛 |
| 馬の壮烈な死に涙を浮がべ手を合わせる者もいた。 |
| 湿原には坪に1株くらいの海坊主(草のかたまり)があり、野営するときはその上に小経木を敷き天幕を張 |
| る。歩哨は火を焚きながら周辺を警戒する。満州にはオオカミがおり、遠吼の聞えてくる夜もあった。 |
| なにぶん湿地帯を歩くのだから靴がぬれる。そうすると、足が水分でふくれてくるし、表面の皮膚が柔かく |
| なってくる。行軍でできたマメがつぶれて破れる。痛いから休憩のときに靴を脱ぐ。ひととき楽になるが、再び |
| はくときが辛い。足がふくれてしまっているのでなかなか入らないのである。マメのつぶれたところからバイキ |
| ンが入って化膿し、歩けなくなる者も出た。疲労が重なって、歩きながら寝むり、足もとをふらつかせ、湿原に |
| 倒れてずぶぬれになる者もあった。背には重い背嚢をかつぎ、肩に銃や機関銃をかついでいるのだ |
| から疲れるにしたがってそれらの重みが肩に食い込んでくる。食物は次第に減ってくるし、ろくなものを少量 |
| しが食べないのだから腹が満たされることはない。 |
| 演習とはいえまさに生地獄。20日ほどたつと、行軍中に3人の兵が苦しみに耐えられず銃で自殺した。 |
| もちろんこの兵たちは戦死ということにされたが、大隊には暗い空気がただよい、笑いが完全に無くなって |
| しまった。兵たちの顔はまさに亡者。ほほはこけ、ヒゲは伸び放題、目はうつろであった。 |
| こんな状況だから、大隊長としてはこれ以上無理は出来ない。このため到着予定を10日ほど延長せざる |
| を得なくなり、師団本部へ食糧の補給を要請した。連絡してほどなく飛行機から食糧が投下された。主食の |
| ほか乾パン、小糠イワシやコンペイ糖などが補給されたが、そのとき、これらを口にしたときのうまさは今も |
| って忘れることができないという。いかにロクなものしか食べていなかったかといえよう。 |
| 食糧の補給を受け、体も休めてやや元気を取り戻した大隊は再び目的地へ向かった。尖兵隊長には若い |
| 将校が交代でその任に当たった。任官ホヤホヤの岡本少尉にも当然順番が回ってきた。尖兵隊は周囲の |
| 状況を判断しながら本隊を無事目的地へ誘導する任務を持たさている。尖兵隊が誤ちをおかすと、気が付い |
| たら敵に包囲されていたということになりかねないのだから、その任は極めて重いのである。したがって尖兵 |
| 隊長は常に神経をとがらせていなければならない。でも満州の大地は広い。歩けども歩けども先に見えるの |
| は地平線で、目標になる集落や川などに行き当たらない。このため進むべき方向を見誤り、修正することが |
| 繰り返された。それでもどうにか目的地の饒河にたどりついた。 |
| 饒河は満・ソ国境を流れるウスリー河の河岸にあり、200戸ほどの集落。河幅は50㍍ほどで対岸にはソ連 |
| の歩哨の立つのが見える。小さな集落とはいえ戦略上は極めて重要な地であった。 |
| 第一大隊は対岸のソ連陣地の配備がどうなっているかの情報を集め、毎日関東軍司令部と参謀本部へ |
| 報告、そのかたわら非常の場合に備えて陣地の構築に当たった。また越冬準備も始まった。演習という名 |
| 目で、実際は、いつ発生するかわからない戦いに備えたことがこれで裏付けられた。岡本もこのような状況 |
| に「もう帰れんかも知れん」と腹をくくった。 |
| 冬に備えて、船の中央両側に水草を取り付けた輸送船が、一週に一度の割でやってきた。糧秣を運ぶの |
| が主目的であった。 |
| そういった時期、つまり昭和16年10月に関東地方(主として埼玉県)がら初年兵がやってきた。そして岡本 |
| は彼等の教官を命ぜられた。岡本が初年兵時代の班長連中が班長を務めてくれたので気心が通じ、彼は |
| 大いに助かった。短期間で教育を終え、その後、各中隊から選ばれた狙撃兵の教育を命せられた。 |
| 人を教育するということはむつかしい。岡本が相ついで教育を担当させられたのは、彼がすぐれた指導力 |
| を持つ将校だったということであろう。 |
| この間、第一大隊が血の出るような苦労を重ねて切り開いた宝清−饒河までの道は、工兵隊がトラック |
| の通れる軍用道路として使用できるよう作業を開始した。新しい戦いに備えたものであることはいうまでも |
| ない。12月8日には日米開戦の報が人り、満ソ国境でもピーンとした緊張感がみなぎり、陣地構築と情報 |
| 収集が一段と活発になった。そのなかでも情報収集はとくに重要。岡本は現地へ駐留後、3代目の情報主 |
| 任となった。 |
| 情報班は、饒河郊外にある大楠山、小楠山と名付けた小高い山でウスリー江の対岸にあるソ連の陣地の |
| 状況や、軍隊、物資の動きを観察した。 |
| 大楠山には115倍の双眼鏡を備えつけた。関東軍全体で2つしかない重要な兵器だった。とにかく饒河は、 |
| 東ソ鉄道、スターリン街道の監視に欠かせない場所だったのだから当然であった。その重要な地点で、若い |
| 岡本が情報責任者に任名されたのだから、岡本にとってはまことに名誉なことではあったが、彼は神経の休 |
| まるときが無かった。絶対に失敗は許されないからである。判断を誤ると関東軍全体の運命にかかわるからだ。 |
| 情報収集は、交代で四六時中双眼鏡を利用して対岸を監視して行う。 |
| 例えば機関銃、高射砲、遠距離砲、側射砲、そして鉄条網の位置などをはじめ、毎日10本ぐらい入る列車 |
| の状況。貨物車の名称、積載荷物まで判断する。無がい車の場合はシートの形で、戦車かトラックかを判断、 |
| 有がい車ならば車輛のスプリングの張り具合で荷物を積載しているか、いないかを判断、積載の場合はその |
| 中味を想像する。東ソ鉄道の沿線に対する監視所で貨物列車の動きをみていると、自然にわかってくる。 |
| また山の向う側で見えないところについては、聞こえてくる銃声の内容で、訓練の様子が読みとれるので |
| ある。このほか飛行機の発着状況など、岡本は情報を慎重に分類、分析して、毎日関東軍へ報告した。 |
| この情報収集は日本軍側が一方的に行うものではない。ソ連側も同様である。鼻毛からツララが下がる |
| ような極寒の季節、ウスリー江をはさんで日ソが開戦に備え、火花を散らしていたのである。 |
| こんな中での唯一楽しみは、大隊に配属されている同期の人たちと会うことであった。岡本が連絡係となっ |
| て、日時と場所を決め、盃をかわした。集まった人たちは坪川健一(第一中隊)、本田勇(第二中隊)、上田 |
| 広輝(第三中隊)、有馬藤吉(第四中隊)、上田清隆(機関銃中隊)、浅井寛(歩兵砲隊)らであった。いずれ |
| も、岡本の駐在する饒河の集落からさはど遠くないところにいるのでよほどのことがない限りは集まった。 |
| 日本内地からしてみればまさに地の果てのようなところだが、こんなところにも日本の商人は進出してきた。 |
| もちろん軍の要請によるものだと思うが、将校用として「きまま」「君の家」という2軒の飲み屋があり(兵隊用 |
| もあった)、それぞれ女性が3〜4人いた。将校たちの話し相手はもちろん、男性の欲望に応していたことは想 |
| 像に難くない。バラックに毛の生えたような飲み屋ではあったが、そこに女性がおり、自由に酒が飲めるとい |
| うことは、明日をも知れぬ身で厳しい生活を送っている将校たちにとってはオアシス的な存在だったのである。 |
| そんな生活を送っていたある日、岡本が初年兵時代に内務班長をしていた、南条町出身の桂一雄が奇縁 |
| にも岡本と同じ第一大隊におり、所用で内地へ出張することになった。桂からそのことを聞いた岡本は「軍務 |
| だから無理はしないでほしいが、もし時間があったらぜひ福井の自宅に立ち寄って、おれに代って亡き父の |
| 霊に線香をお供えしてくれないか。また母がなにかと心配していると思うので、元気で頑張っていることを伝 |
| えてほしい」と頼んだ。桂は岡本の親思いに心を打たれ、依頼された通り岡本宅に寄り、仏壇にお参りしたあ |
| と、母「みつ」と姉に、満州で岡本が元気で過ごしていることを伝えた。2人は涙を流して喜んだそうで、帰隊 |
| 後、岡本にそのことを話すと、彼の目もうるんだという。 |